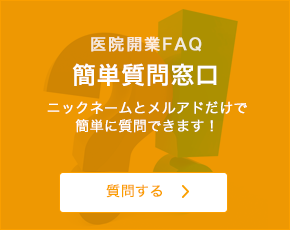コラム・お知らせ
2019年9月6日
昨年以降の調剤薬局M&Aの動向とまとめ
AcePartners代表の柴田(裕)でございます。
相変わらず話題が食べ物ばかりになっておりましたので、我々の基幹業務での話題を取り上げて
みました。調剤薬局のM&Aについて、小職の考えは世間の流れと異なりますが、一般的な流れ
についてまとめています。
大手企業は本業加速型M&Aで大型案件重視の傾向・小規模企業は売りづらい時代へ
昨年の段階で、上場・大手企業は積極的にM&Aでの出店をしたい意向がIRなどに表れており、
昨年4月に公表された日本調剤「2030年に向けた長期ビジョン」には、同社のみでシェア10%・
売上1兆円企業を目指すと発表されている通り、各社の拡大傾向に変化はない。
それも他事業に手を広げるわけでもなく、あくまで本業に集中する“本業加速型”での成長を重視して
いる。
しかし、そのM&Aの姿勢については昨年に入り状況が激変している。これについては報酬改定が
絡んでくるが、集中率・店舗規模・店舗数など、案件内容をかなり精査するようになっている。
ご存知のように大手・準大手企業に対しては集中率85%以上の店舗を譲受ける場合、調剤基本料1が
算定できなくなり、それに伴い地域支援体制加算も算定できない可能性が高くなっている。
そうなると、単一店舗での収益改善が困難(むしろマイナス)になり、さらには今後の報酬改定で
仮にその店舗の収益が下落した場合の収益改善が更に困難になる。その為、複数店舗案件のM&Aに
よりいっそう重きを置くようになった。
複数店舗であれば技術料が多少落ち込んだとしても、ドミナント戦略が取れ、コスト削減や薬剤師の
調整等も行うことができ、1店舗を譲受ける場合に比べて収益改善も早く、且つ打てる施策が多い
というメリットがある。1店舗を10回譲受けることに比べ、10店舗を1回で譲受けたほうがよい
という考えがより強く表れた年となった。
反対に1店舗企業の案件は徐々に譲渡がし辛くなっており、今後の改定次第では全く譲渡ができなく
なる時代に突入することは容易に想像できる。先に述べた様に上場・大手企業を筆頭に1店舗案件を
敬遠しだしており、代わりの譲受け企業として手を挙げだした中堅企業は、金額等の条件が大手ほど
良いものにはなく、譲渡側の想いと折り合いが付かないようになっている。
かつてのドラッグストア業界が同じ状況で、1店舗企業が譲渡できなくなってから5店舗程度の案件
が次に譲渡できなくなり、更には10店舗案件ですら難しくなり、現在では50店舗以上の大規模の
案件のみが譲渡できる層となっている。
調剤薬局業界においても同じ軌跡を辿る事は間違いないと思われる。
各地域の有名企業の戦略的譲渡、後継者のための譲渡も
昨年も各地域の有名薬局、地方中堅企業が大手傘下に下った。

どの企業も財務内容や収益面では申し分なく、薬剤師も豊富に抱えている企業である。これらの企業は
自社での哲学や方針が明確で、薬局機能としても非常にレベルの高い企業である。それらの企業がどん
どん大手傘下にはいっているのは、先に述べた大手企業の状況の変化も関連するところがある。大手
企業は上述の通り、中堅企業の譲受けに必死であり、その譲受け条件や譲渡企業の要望に対して非常に
柔軟になりつつある。そのため中堅企業としても、ニーズに合致した企業が見つかりやすくなってきて
いる。
社長が社長のままで残り経営をしたい、親族や腹心を次期社長にしたい、大手の経営資源を良い意味で
利用して自社を発展させたい。さまざまな要望がある中で、それをのむ企業がでてきている。譲渡を
経験した中堅企業オーナーによれば「大手と一緒になって、一番変わったのはリスクをよりいっそう
取ること・チャレンジができるようになったこと」という話もある。少し前であれば、大手が譲受ける
と、社長は交代、会社は合併、看板も統一化という印象があるが、現在は状況が一変している。
最近の例であるは、経営陣はそのまま続投・合併されること無く社名は残る。更には薬局の看板等も
全く変更無しという具合である。もちろん、大手企業によって考え方は違ってはくるが、それぞれの
地域の良さやブランドを大切にする企業が増えている。
譲渡側からずれば、株の承継問題も解決・意中の後継者に経営を承継できて、後継者においても個人
保証等のリスクなく、のびのびよりよい薬局作り、運営に集中できる。
「長い間尽くしてくれた取締役に次を任せたい。」
「能力有無の点で判断がつく段階ではないが、立候補する後継者にチャンス与えたい。」
「後継者候補に能力はあるが、株を引き継ぐ資金が無い。」
などの悩みを抱えるケースが増えてきている。今となっては、このすべてがM&Aで解決できるのも、
現在の調剤薬局業界ならではの傾向ではないだろうか…。
ファンドやブローカーの出現!正しいM&Aを再認識する必要性が高まる
業界再編が進んでいる調剤薬局業界、そこに商機をにらんだ企業が多く参入してくる。これについては
歓迎すべきことだ。M&Aが一般的な手法で、薬局にとってベストな選択肢であれば積極的に活用する。
そのような雰囲気づくりは日本全体に必要なことである。
しかし、参入企業が増えるにあたり、その質には十分配慮しないといけない。決算書や月計表のみを
見て、高値で譲渡できることをアピールするブローカーなどは要注意で、単に顧客の目を引きたいだけ
で、最終的に買収監査時に大きく減額を強いるのが関の山である。
また、最初だけ高値で提示をし、基本合意で独占交渉権を得て、その後の買収監査でもっともらしく
減額を要請するファンドなども横行している。
M&Aを活用する企業が多く参入することは歓迎すべきだが、正しい手順・やり方でM&Aを進めなけ
れば決してうまくいかないものである。業界全体が再度その認識を高めるべきであると希望する。
本年10月にはの薬価改定、消費増税、次回の報酬改定への議論がスタートと、まさに業界の変化が大きな
年となる。常に先を見据えてリアルタイムで情報収集し、適切な経営判断をするべきと思う。
私たちにお気軽にお問い合わせください
医院開業についての相談や物件の詳しい情報などは電話もしくはお問い合わせフォームにてお気軽にご連絡ください。
- 0798-20-8311
- 平日10:00~18:00 土日祝日休み
コラム・お知らせ人気記事
-
2017年1月14日
-
2016年10月12日
-
2020年5月27日
-
2018年7月30日
-
2016年8月30日